
1987年に制作され、同年日本でも公開された『ハンバーガー・ヒル』が4月16日からリバイバル公開されます。
正直このニュースを初めて聞いたときは、自分の耳を疑いました。
なぜ、映画史の中から忘れ去られているかのようなこの作品が、今頃になってリバイバル?
しかし一方では、自分と同じようにこの作品を支持してくれている人が一定数いたのだなと、改めて我が意を得た気持でもありました。
『ハンバーガー・ヒル』、これこそは私が思うに、少なくともヴェトナム戦争を描いた映画の中で最高傑作!
戦争映画全体から見ても10本の指にカウントできる、名作中の名作と信じて疑わない作品です。
1970~1980年代のヴェトナム戦争映画の流れ
『ハンバーガー・ヒル』そのものを語る前に、公開当時の1980年代の戦争映画の経緯みたいなものについて軽くお伝えしておきましょう。
以前『ラスト・フル・メジャー 知られざる英雄の真実』(19)を紹介させていただいたときも触れたことですが、ヴェトナム戦争たけなわの1960年代後半はハリウッドきってのタカ派ジョン・ウェインが監督主演したヴェトナム戦争肯定映画『グリーン・ベレー』(67)が作られ、それに反発する世界中の映画人が『ベトナムから遠く離れて』(67/フランス)『ベトナム』(69/日本)などの反戦運動映画などを発表したりしていたものでした。
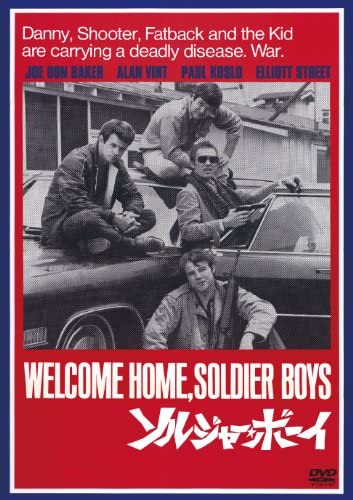
やがて1970年代に入り、アメリカは敗北を認めざるを得ない状況へと追いやられ、それに呼応し合う形でヴェトナムの戦場から帰還した兵士たちのその後を描いた映画が『ソルジャー・ボーイ』(72)以降定期的に作られるようになっていきます。
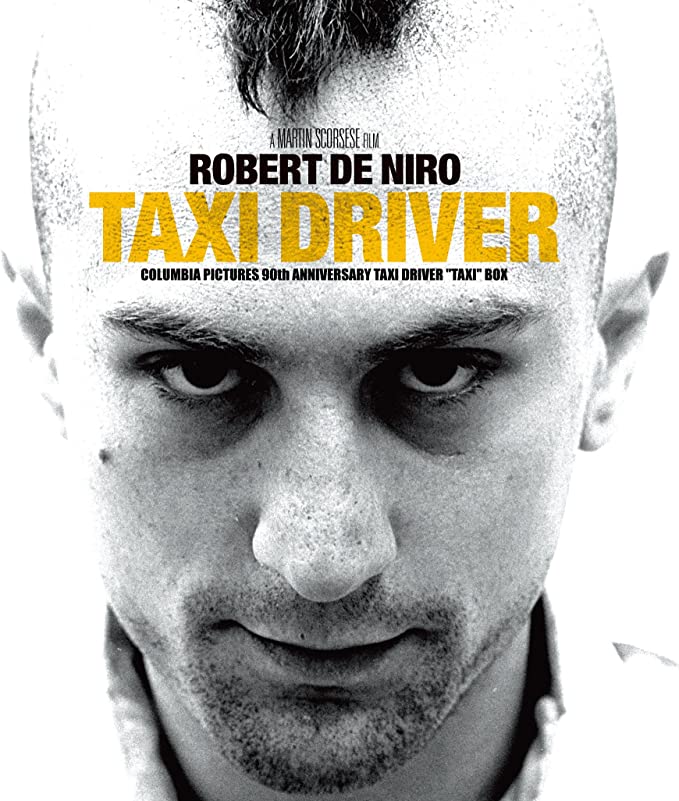
特に『タクシー・ドライバー』(76)『ローリング・サンダー』(77)『ドッグ・ドルジャー』(78)といった帰還兵らがアメリカの闇と向き合うヴァイオレンス・アクション路線と、『幸福の旅路』(77)『ディア・ハンター』(78)『帰郷』(78)など戦場で心の傷を負った人々の苦悩を描いたものとに大きく二分。
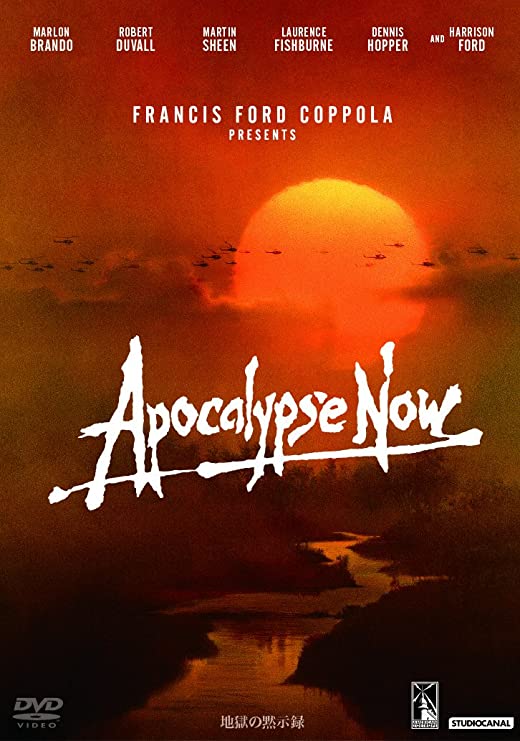
60年代後半より上演されて人気を博した反戦ロック・ミュージカル「ヘアー」も1979年に映画化されました。
同時に『戦場』(77)『地獄の黙示録』(79)とヴェトナムの戦場そのものを描いた作品も登場し、特に後者は世界中を賛否の嵐に巻き込む問題作として話題になりましたが、前者も『ハンバーガー・ヒル』同様に知る人ぞ知る“隠れた戦場映画の名作”の誉れ高い作品です。

1980年代に入ると、帰還兵に対するアメリカ国民の偏見などもモチーフにしたアクション映画『ランボー』(81)が作られますが、このときの監督テッド・コチェフはその後、ヴェトナムの戦場で行方不明(=MIA)となった我が子を救出しようとする父とその仲間たちの無謀なミッションを描いた『地獄の7人』(83)を発表。
これがヴェトナムの敗北から立ち直り、再び強きアメリカを再建しようと説く1980年代レーガン政権の気風ともマッチしたか、その後も続々とMIA映画が作られるようになっていきます。
前作で自国アメリカの人々から心無い仕打ちを受けたランボーも続編『ランボー怒りの脱出』(85)でヴェトナムに舞い戻り、以後、主演のシルヴェスター・スタローンの人気を支える大ヒット・シリーズと化していきます。

また一足先に製作されたチャック・ノリス主演の『地獄のヒーロー』(84)もシリーズ化。

しかし、こういった風潮に異を唱えるかのように1986年『プラトーン』が登場します。
これはヴェトナム帰還兵でもあったオリヴァー・ストーン監督の実体験に基づく作品で、戦場におけるさまざまな過酷な現実を露にしたもので、アカデミー賞作品・監督・編集・録音賞を受賞。
これによって一気にヴェトナム戦争映画がブームと化していき、当時勃興し始めたビデオレンタル店ラッシュの中、劇場未公開作品までも多数日本で鑑賞することが可能となっていきました。
そして『ハンバーガー・ヒル』は、『プラトーン』(日本公開は1987年4月29日)とスタンリー・キューブリック監督の超大作『フルメタル・ジャケット』(87/日本公開は1988年3月19日)の間に挟まれるような形で、1987年9月12日に日本公開されました。
–{人間をミンチにしていく地獄 それでも「俺たちは丘を取る」}–
人間をミンチにしていく地獄それでも「俺たちは丘を取る」
『ハンバーガー・ヒル』は1969年、南ヴェトナムのアシャウ渓谷にある丘“ドン・アプ・ビア”=937高地をめぐってアメリカ軍第101空挺師団と北ヴェトナム軍との間で繰り広げられた激戦“アパッチ・スノー作戦”を映画化したものです。
この戦い、日露戦争の一大激戦を描いた『二百三高地』(80)同様、丘を奪取するために敵味方を問わず多くの兵士たちの血が流れていきます。
いや、血どころか「この丘は俺たちをミンチにしようとしているのか!」と戦場の兵士たちが叫んだとも言われるように、そこは生死を問わず人の肉片が飛び散る惨状を呈する地獄でもありました。

本作はそうした地獄の中に放り込まれ、丘を奪取する目的もよくわからず、ただただ突撃を繰り返しては同胞がひとり、またひとりと減っていく日常を淡々とドキュメンタリー・タッチで捉えていきます。
キャストも初公開当時は無名の俳優ばかり(後にディラン・マクダーモットやドン・チードルらがスターになっていきました)。
撮影監督は、それまで『遠すぎた橋』(77)など数多くの戦争映画でB班撮影を担当し、本作の後で『ランボー3怒りのアフガン』で監督デビューを果たすピーター・マクドナルド。技巧を凝らした画が一切ないのも美徳のひとつです。
音楽は現代音楽界の名匠フィリップ・グラスですが、彼の音楽そのものが使われているのはメインタイトルとエンドタイトル、そしてクライマックスのみというストイックな趣向。そして劇中挿入歌としてアニマルズの《朝日のない街》も効果的に用いられています。
監督は『戦争の犬たち』(80)『チャンピオンズ』(84)『アーノルド・シュワルツェネッガー/ゴリラ』(86)などで知られるイギリス人ジョン・アーヴィン。
彼は英BBCドキュメンタリストとして実際にヴェトナムの戦場へ取材に赴いたキャリアを持っています(つまりはアメリカ人とは異なる異邦人的な目線で戦争を見据えていた)。
そして本作の脚本ジェームズ・カラバトソスもヴェトナムの戦場を知る帰還兵で、『幸福の旅路』も彼の脚本によるもの。

劇中、ディラン・マクダーモット扮する兵士フランツが、現地を取材するマスコミの心ない質問の数々に対して、怒りを抑えながら応えます。
「面白いか? ニュースのネタを探してハゲタカみたいに誰かが死ぬのを待ってる。敵の奴らのほうがお前らよりマシだ。自分の命も懸けないウジ虫どもが、よく聞け。俺たちは必ず丘を取る。そのとき俺たちの写真を撮ったら、頭をぶち抜いてやる」
もしかしたらジェームズ・カラバトソスは、実際にこのような言葉をマスコミに発したのかもしれません。
そしてジョン・アーヴィンは、こういった言葉を聞いたのかもしれません。
本作は反戦的なメッセージが口にすることはほとんどありません。いや、むしろ反戦的な言葉を外野から浴びせられて苦悩する兵士たちの心情をこそ描いています。
そして、だからこそ「俺たちはこの丘を取る」といった台詞が実は好戦的なものでも何でもなく、そうしなければ生きていけない彼らの悲痛な意思表示として辛く胸に残り、ひいては戦争そのものの愚かさが巧みに描出されていくのです。

一方では、戦う意味を求める術もないまま、敵と殺し合うのみの兵士たちにも日常があり、仲間同士の絆が生じたり、逆にほんの些細なことで喧嘩や諍いが起きたりもします。
(歯磨きのシーンなど非常にユニーク。またモラルの問題はさておき、慰安所の娼婦たちがそんな兵士たちにとって数少ない心の拠り所になっていた現実も描かれます)。
やがて戦闘は終わりを迎えますが、兵士たちの胸には、虚無的な想いしか湧き上がっていきません。
そして生き残った者たちは次の戦場へ赴き、また同じような意味のない戦いを繰り返し、やがて母国へ帰還した者たちの中には『タクシー・ドライバー』のトラヴィスや『ディアハンター』の鹿狩り仲間や『ランボー』の主人公のような運命を辿っていくことを、この作品は悲しいまでに冷徹な目線で示唆していくのです。

先にも申しましたが、本作は『プラトーン』と『フルメタル・ジャケット』という二大話題作の狭間に公開されたこともあって知名度は前2作よりも弱かった感があります。
またその後も『地獄の黙示録』のフランシス・フォード・コッポラ監督が描いた戦場が出てこないヴェトナム戦争映画『友よ、風に抱かれて』(87)や、『7月4日に生まれて』(89)『天と地』(93)といったオリヴァー・ストーン監督のヴェトナムものの連打といった話題作が続々公開されていく中、次第に地味な存在と化していきました。
しかし、心ある映画ファンの胸の中にはいつまでも忘れることのない名作であったことが、およそ34年の時を経てのまさかのリバイバルではっきりし、どこか溜飲が下がった想いでもあります。
時あたかもヴェトナム戦場での“英雄”の復権を説く仲間たちの労苦を描いた映画『ラスト・フル・メジャー 知られざる英雄の真実』(19)が公開され、かたや『シカゴ7裁判』(20)ではヴェトナム戦争反対のデモ隊と警官隊が衝突したシカゴ暴動で起訴された7人のでたらめな裁判が明るみにされました。

ヴェトナム戦争終結からおよそ半世紀経とうとしていますが、ようやくアメリカはあの戦争を客観的に見据えられる時期に来ているのかもしれません。
またそれに同調するかのように、今振り返るとまだまだ冷静に成り切れていなかった1980年代ヴェトナム戦争映画の中で、もっとも冷静かつ兵士のひとりひとりに哀悼の意を込めた『ハンバーガー・ヒル』が再評価されるというのも、何かの宿縁なのでしょう。
ぜひともスクリーンでの鑑賞をお勧めいたします。
エンドクレジットに浮かび上がる兵士たちの顔、顔、顔! そして痛烈なメッセージも、ぜひ心に刻んでください。
“WELCOME TO HAMBURGER HILL”
(劇中、この言葉の下に記された文字にもご注目を!)
(文:増當竜也)



