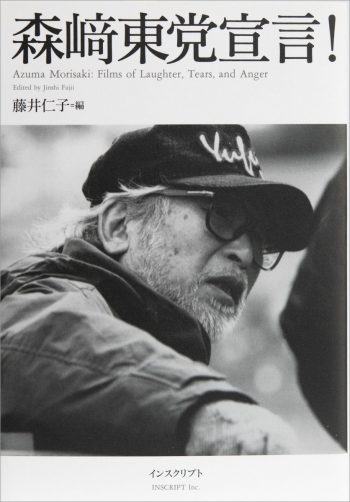
森﨑東監督が本年7月16日に92歳で亡くなられました。
猥雑かつ大らかな笑いの中に庶民の怒りを忍ばせた重喜劇たる“怒劇”の担い手として多くの映画ファンにリスペクトされ続けた森﨑監督の代表作の1本『時代屋の女房』をご紹介したいと思います、その前に彼のキャリアをざっと振り返ってみましょう。
女は度胸、男は愛嬌、生きてるうちが花なのよ!
森﨑東監督は1927年11月19日生まれ。
56年に松竹京都撮影所に助監督として入所。65年より大船撮影所に移籍し、山田洋次監督の『愛の讃歌』(67)『喜劇一発大必勝』(69)などの脚本を手掛けるようになり、山田監督から厚い信頼を置かれるようになっていきます。
(ご存じ69年のレジェンド・シリーズ第1作『男はつらいよ』の併映だった渡辺祐介監督作品『喜劇 深夜族』の脚本も、彼と宮川一郎が共同で担当)。

69年、遅咲きながらも『喜劇 女は度胸』(69)で監督デビュー。
以後、『喜劇 女生きてます』(71)『喜劇 女は男のふるさとヨ』(71)『喜劇 女売り出します』(72)と、あたかも主演の倍賞美津子をミューズとみなしたかのようなバイタリティ豊かな“女”シリーズで評価されました。
(ちなみに『喜劇 女は度胸』の直後には、タイトル的にも対になっている渥美清主演『喜劇 男は愛嬌』を撮っています)

また同時期には寅さんシリーズ第3作『男はつらいよフーテンの寅』(70)を演出(当時、山田洋次監督はシリーズ3&4作目の演出を辞退し、自作『家族』演出に専念)。山田監督版とは一味違う寅さんの魅力が放たれていました。
さらには黒澤明監督作品の大胆なリメイク『野良犬』(73)や、NHK朝のテレビ小説の映画版『藍より青く』(73)など多彩なジャンルを手掛けており、70年代前半の松竹映画を語る上で絶対に欠かせない存在となっていきます。
が、74年にフリーになり、東映に招かれてストリッパーのヒモを主人公にした重喜劇の快作『喜劇 特出しヒモ天国』(75)を手掛けたり、スタントマンの伯父と8ミリ映画青年の関わりから人生の悲哀を吐露していく名作『黒木太郎の愛と冒険』(77)を自主製作(ちなみにこのとき映画青年を演じたのが、インディ映画の伝説的名作『ゴンドラ』を監督することになるカリスマAV監督TOHJIROこと伊藤智生です)。
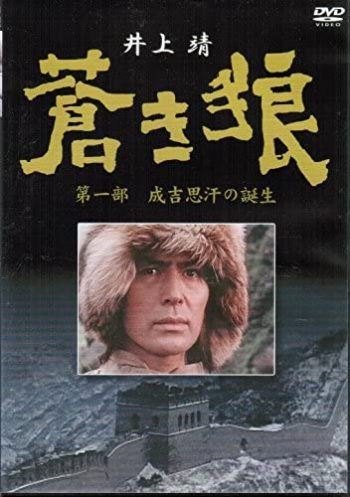
かと思うと、1980年にはチンギス・ハーン(加藤剛)の生涯を描いたTVミニ・シリーズ超大作『蒼き狼 成吉思汗の生涯』(原田隆司と共同)でスケール豊かな骨太演出を披露しています。

80年代に入ると、ピンク映画の撮影現場を通してカツドウヤの凱歌を描いた『ロケーション』(84)、“女”シリーズの延長線で、なおかつ痛烈な体制批判をダイナミックに盛り込んだ、倍賞美津子主演の『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』(85)を発表し、その評価はますます高まっていきます。
その一方で、寅さんシリーズの併映として取り組んだ『塀の中の懲りない面々』(87/38作『男はつらいよ 寅次郎知床慕情』の併映)、『女咲かせます』(87/39作『同 寅次郎物語』の併映)、『夢見通りの人々』(88/41作目『同 寅次郎心の旅路』の併映)はそれぞれメインに勝るとも劣らない魅力を放ちつつ、マンネリ化していたシリーズの企画&興行にも刺激を与えることに成功。
また『女咲かせます』と『夢見通りの人々』の狭間の寅さんシリーズの併映として、栗山富夫監督の『釣りバカ日誌』(88/40作『寅次郎サラダ記念日』の併映)が登場し、瞬く間に人気を博してシリーズ化されていきますが、やがて森﨑監督に厚い信頼を置く山田洋次監督に招かれて撮った『釣りバカ日誌スペシャル』(96)は、笑いの中にシェークスピア的な人間の愛憎と嫉妬を盛り込んだ、まさに森﨑“怒劇”としても屹立していました。

その後も三國連太郎&佐藤浩市の親子共演が話題となった『美味しんぼ』(96)、浅田次郎原作『ラブ・レター」(98)、『生きてるうちが~』の後日譚のようでもある『ニワトリはハダシだ』(03)と大いに気を吐き、結果的に遺作となった『ペコロスの母に会いに行く』(13)は、キネマ旬報ベスト・テンの第1位を獲得しています。

「何も言わず何も聞かず~」に込められた人の情の切なさ

さて、前置きが長くなってしまいましたが、そんな森﨑東監督作品の中から、今回は1983年度作品『時代屋の女房』を紹介したいと思います。
第87回直木賞を受賞した村松友視の同名小説を原作にした人情喜劇であり、悲劇であり、そしてミステリアスなラブ・ストーリーであるという、森﨑映画の代名詞“怒劇”の域を優に超越した名作です。
舞台は東京・大井町で35歳の独身・安さん(渡瀬恒彦)が営む古道具屋“時代屋”。
ある夏の日、野良猫を抱え、銀色の日傘を差した真弓(夏目雅子)と名乗る女性が時代屋に現れ、そのまま店に居ついてしまいました。
彼女はまるで猫のように、時折ふっと店を出たまま行方をくらませ、しばらくすると何事もなかったかのように帰ってきます。
しかし真弓は自身のことを何も語ろうとはせず、安さんも聞こうとはしません。
「何も言わず、何も聞かずが都会の流儀」
こうしたふたりの関係性ですが、さすがに今度は真弓が出て行ってから妙に長くなっているようで……。
このように本作は、一定の距離感を保ちつつ、どこか心惹かれ合う男女の機微を切々と描いていきます。
森﨑映画の特徴ともいえる“怒劇”としての構えは他作品に比べると控えめで、その意味では彼の映画に精通してない方も入り込みやすい作品と言えるでしょう。
そもそも森﨑映画は怒劇という言葉の“怒”の部分がひとり歩きしてしまい、彼の本質ともいえる深い人間愛の要素があまり語られていない感も、個人的には受けたりしています。
森﨑映画の底辺に精通しているのはやはり“愛”であり、だからこそ理不尽な社会に対する“怒”が頭をもたげていく、それこそが森﨑映画の真情ともいえるでしょう。
「何も言わず、何も聞かずが都会の流儀」
一見クールでサバサバしているかのような人間関係ではありますが、しかしながらその奥には意外と相手に対するジレンマやら嫉妬、不安などドロドロした感情が潜んでいるものであり、それを何とか押し隠しながら日々をやり過ごしていく人の情。
これを肯定することで、夏目雅子のミステリアスな風情もまた一段と美しく映えわたっていくのです。
そう、森﨑映画のヒロインは、どのような境遇の女性であっても、常に美しく捉えられていきます。
その筆頭は当然ながら“女”シリーズから『黒木太郎の愛と冒険』『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』『ニワトリはハダシだ』と森﨑映画の節目節目に登場してくる倍賞美津子である事に義を唱える方はほとんどいないでしょう。
しかしながら、実は『野良犬』『藍より青く』『女咲かせます』の松坂慶子も、『喜劇 特出しヒモ天国』の池玲子や芹明香なども、『ロケーション』の大楠道代&美保純(特にこの映画の彼女はすごい!)も、『夢見通りの人々』の南果歩も、『釣りバカ日誌スペシャル』の石田えりも、『ラブ・レター』の耿忠(タン・チュウ)も、そして『ペコロスの母に会いに行く』のおばあちゃんヒロイン赤木春恵も、その他の森﨑映画のヒロインたちも、彼女に負けず劣らずの美を放っているのです。
もちろん本作の夏目雅子も例外ではありません!
こうした目線で本作を、そして森﨑映画を鑑賞していただけると、またいろいろと新たな発見が出てくることでしょう。
(文:増當竜也)



